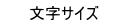病院概要
院長挨拶

当院は地域の中核病院として、患者さんを中心とした医療を実践し、地域の皆さんが安心して健康に暮らせることを第一に考え診療を行っております。
登米市は医療過疎、少子高齢化という問題を長年抱えてきました。特に医師不足、医師の高齢化は全国平均を大きく下回っており、最も解決すべき重要な課題でした。それに対して市や県は、医学生への奨学金制度を設け医師の育成に努めてきました。その医学生たちは医師となって各地の病院で研鑽を積んだのちに専門医となり、数年前から当院で働き始めております。今後もこの制度を利用した医師たちが勤務する予定となっており、医師の確保に役立っています。また基幹型臨床研修病院として初期研修医の受け入れも行っています。この研修医たちは「地域に根ざし、全人的な治療ができる医者になりたい」という志をもって、敢えて大病院ではなく当院での研修を志望してきました。彼らが研修を終え立派な医師となって、将来的にはまた当院で働いてくれるよう、大切に指導しているところです。まだまだ診察中は不慣れなところがありますが、市民の皆さんには温かく見守っていただければ幸いです。
一方で少子高齢化、人口減少は全国的な問題であり、なかなか解決の糸口が見つからないのが現状です。そこで問題になるのが、将来の生活の場の提供です。いつまでも元気に自宅で暮らせることが目標ですが、年齢に伴う体力の衰えや病気、老老介護などで入院や施設入所が必要となる方もいらっしゃいます。そこで官民が一体となって、治療と生活の場を連携させながら地域全体で患者さんを見守る地域包括ケアシステムを構築しています。その中で当院は多職種と連携をとり、地域の医療機関や介護施設とのネットワークを使いながら一人ひとりのニーズに合わせた医療サービスを提供しています。またナースプラクティショナー(許可範囲内での診察・治療の資格を持った看護師)を施設や訪問看護に派遣し、早期発見、早期治療に繋げる取り組みも試みています。今後は、デジタル技術を利用した施設間の情報共有、遠隔診療や業務の効率化といったものにも取り組んでいく必要があると考えています。これには財源やセキュリティーの問題など解決すべき問題がありますが、優先課題の一つとして捉えているところです。
また人材や設備の確保、財政の効率化などを図るため、市立3病院間で機能を分担しています。当院は急性期治療に特化し、慢性期の治療は米谷病院と豊里病院が担いますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
これからも地域に密着した医療の提供、環境整備や教育に尽力してまいりますので、宜しくお願いいたします。
院長 髙橋 雄大
病院理念
病院理念
基本方針
1.患者さんの立場にたった思いやりある態度で接し、いつでも安心して受診できる病院であるように努めます。
1.他の医療機関及び介護、福祉施設等と緊密に連携し、在宅復帰に向けた地域包括ケア体制の充実を図っていきます。
1.職員は最新の医療情報や技術の習得に努め、医療水準の維持向上に努めます。
1.職場環境を整備して、職員が働き甲斐を実感でき、他に誇れる職場づくりをします。
1.公的医療機関として、政策医療を担いながら効率的な運営に努め、経営の安定化を図ります。
患者さんの権利と義務
権利
●患者さんには、誰でも良質で安全な医療を公平に受ける権利があります。
●患者さんには、病状と経過及び検査や治療内容などについてわかりやすい説明を求める権利があります。
●患者さんには、十分な説明と情報を得て自らの意思で治療方法を決定したり、他の医療機関を選択する権利があります。
●患者さんには、診療上提示した個人情報やプライバシーの秘匿を求める権利があります。
義務
●患者さんには、診療が円滑に行われるように病院で定めた規則を守る義務があります。
●患者さんには、診療に際して医療従事者と協力する義務があります。
●患者さんには、受けた医療に対して診療費を遅滞無く支払う義務があります。
施設概要
| 施設名 | 登米市立登米市民病院 |
|---|---|
| 所在地 |
〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字下田中25番地 TEL&FAX 0220-22-5511(代表) |
| 開設者 | 登米市長 熊谷 康信 |
| 病院事業管理者 | 登米市病院事業管理者 松本 宏 |
| 院長 | 院長 髙橋 雄大 |
| 建物構造 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上6階建 鉄筋コンクリート造6階建 |
| 規模 |
敷地面積16,992m2 建築面積 4,117m2 延床面積17,587m2 |
| 駐車場台数 | 306台 |
| 交通機関情報 |
●JR東北本線 瀬峰駅より車で約20分 ●東北自動車道 築館I.Cより車で30分 ●三陸縦貫自動車道 登米I.Cより車で15分 ●JR東北新幹線 くりこま高原駅より車で30分 ●JR仙台駅前(さくらの仙台店前)乗り場より高速バスで95分 (登米市役所より徒歩10分) |
診療機能
| 診療科 | 内科 消化器内科 小児科 外科 乳腺外科 整形外科 皮膚科 眼科 泌尿器科 産婦人科 耳鼻咽喉科 放射線科 リハビリテーション科 麻酔科 人工透析内科 |
|---|---|
| 稼働病床数 | 一般病床 198床 (うち地域包括医療病床 53床、回復期リハビリテーション病床 30床) |
| 看護体制 | 一般病棟 10対1看護 |
| 外来診療日 | 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始12月29日~1月3日は除く)科によって診療曜日、時間が異なりますので、外来医師担当表をご覧ください。 |
| 主な指定・告示等 | 保健医療機関 労災保険指定医療機関 生活保護法指定医療機関 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 指定自立支援医療機関(更生医療) 結核指定医療機関 被爆者一般疾患医療機関 救急告示病院 災害拠点病院 臨床研修指定病院 肝疾患に関する専門医療機関 |
| 学会認定等 |
日本内科学会認定医制度教育関連病院 日本外科学会外科専門医制度修練施設 日本整形外科学会専門医研修施設 マンモグラフィ(乳房エックス線写真)検診認定施設 日本病院総合診療医学会認定施設 一般社団法人日本病院会病院総合医育成プログラム認定 地域総合診療専門研修プログラム認定施設 |
| 連携認定施設 |
東北大学病院地域医療連携施設 宮城県こども病院地域医療連携登録医療機関 |
| 主な医療機器 |
MRIシステム CT装置 乳房X線システム |
沿革(あゆみ)
| 昭和25年8月 | 宮城県厚生連佐沼病院開院45床 |
|---|---|
| 昭和27年4月 | 病床数75床に増床 |
| 昭和29年3月 |
迫町外3町組合立伝染病床20床併設 結核病床20床新設 |
| 昭和30年11月 |
宮城県厚生連より迫町に委譲 「公立佐沼病院」と改称 |
| 昭和42年1月 | 管理棟及び病棟増改築竣工、病床数を180床に増床 |
| 昭和49年3月 | 救急告示病院指定 |
| 昭和50年5月 | 増改築竣工、病床数を205床に増床 |
| 昭和54年5月 | 伝染病床20床を廃止 |
| 昭和60年1月 | 結核病床20床を廃止、一般病床225床に増床 |
| 昭和61年3月 | 病床数を245床に増床 |
| 昭和61年7月 | 「公立佐沼総合病院」と改称 |
| 平成6年12月 | 本館建築工事竣工 |
| 平成7年9月 | 南館改修工事竣工 |
| 平成7年10月 | 病床数を300床に増床 |
| 平成9年3月 | 災害拠点病院指定 |
| 平成10年10月 | MRI棟竣工 |
| 平成17年4月 | 登米市合併により「登米市立佐沼病院」と改称 |
| 平成22年2月 | 南館耐震補強工事施工 |
| 平成23年4月 | 「登米市立登米市民病院」と改称 |
| 平成23年5月 |
許可病床数258床に減床 南館耐震補強工事竣工 |
| 平成23年6月 | 一般病床30床を回復期リハビリテーション病棟に転換 |
| 平成25年7月 | 救急外来棟・地域医療連携センター竣工 |
| 平成26年4月 | 一般病床2床を陰圧室に転換 |
| 平成28年8月 | 一般病床29床を地域包括ケア病棟に転換 |
| 令和元年12月 | 許可病床数を198床に減床 (地域包括ケア病棟16床を廃止) |
| 令和2年6月 | よねやま診療所で行っていた人工透析機能を移転し、人工透析内科を設置 |
| 令和2年6月 | 地域包括ケア病床16床を新設 |
| 令和3年2月 | 基幹型臨床研修病院指定 |
| 令和5年4月 | 地域包括ケア病床16床を急性期一般病床に転換 |
| 令和7年3月 | 一般病床53床を地域包括医療病棟に転換 |
院内感染対策指針
1.感染管理のための基本的な考え方
2.基本方針
② 全職員は、標準予防策、感染経路別予防策を遵守し、院内感染の発生予防、拡散防止に努める。
③ 全職員は、自らの健康に留意し、ワクチン予防接種や汚染事故防止など職業感染対策に努める。
④ 当院は、地域の医療機関等と連携し、相互に院内感染防止対策の質の向上を図るよう努める。
3.用語の定義
病院環境下で原疾患とは別に新たに罹患した感染症を院内感染といい、病院外で発症しても院内感染という。
2)医療関連感染
急性期病院、長期療養施設、クリニック、在宅ケアなどを含む医療機関において新たに罹患した感染症を医療関連感染
(HAI;Healthcare Associated Infection)という。
3)市中感染
病院内で発症しても病院外で罹患した感染症を市中感染という。
4)院内感染防止対策の対象者
院内感染防止対策の対象者は、入院・外来患者、来院者、当院に勤務する全職員、さらには院外関連企業の職員
を含む。
4.感染制御のための組織に関する基本事項
院内感染対策委員会(以下ICC)は病院長の諮問委員会であり、感染防止対策に関する最終の意思決定機関である。病院における院内感染防止対策に関する業務の円滑な運営および適正化・効率化を推進するため、毎月1 回定期的に開催し審議する。また、緊急時は臨時委員会を開催する。
(1) 構成
① 病院長、関係各部門責任者、安全衛生に関する知識と経験を有する者で組織する。
② 委員長は、病院長が任命する。
③ 委員長は、必要と認めたとき、関係職員の出席を求め、意見をきくことができる。
(2)院内感染対策委員長の業務について
① 委員長は、感染管理に十分な経験を有した医師、あるいは、感染管理認定看護師、あるいは、インフェクション
コントロールスタッフ(ICS)養成講習会修了者、その他の適格者のいずれかで、院長が適任と判断したものが担う。
② 委員長は、感染制御に対する対策委員会(院内感染対策委員会)を組織・運営する。
③ 委員長は、院長より感染対策に関する権限を委譲されると共に責任を持つ。また、重要事項を定期的に院長に報告
する責務を有する。
④ 重要な検討事項、異常な感染症発生時及び発生が疑われた際には、その状況及び院内感染の対象者への対応などを
速やかに院長に報告する。
⑤ 異常な感染症が発生した場合、委員会の中心となって速やかに発生の原因を究明し、改善策を検討するための
指揮官となり、対策が円滑に実施されるよう監視し評価する。
⑥ 職員教育(集団と個別教育)の企画遂行を積極的に支援する。
(3)主な審議事項
① 院内感染防止対策の検討、支援
② 抗菌薬適正使用の検討、支援
③ 院内感染症の発生動向調査、微生物および耐性菌サーベイランスに関する事項
④ 医療関連感染サーベイランスに関する事項
⑤ 院内感染防止対策マニュアルの検討、承認
⑥ 院内感染防止対策における器材、対策、システム変更に関する審議、承認
⑦ 院内感染防止対策徹底のための職員教育の推進
2) 感染防止対策部門
院内感染等の発生防止に関する業務を行うため当院に感染防止対策部を置く。感染防止対策部門は、院内感染防止対策に関わる全てに関与し、抗菌薬の適正使用に関して中心的な役割を担う。また、日常的な感染対策業務の実務を担う。
(1)院内感染対策管理者(院内感染対策委員長)の業務
院内感染対策管理者は、ICT業務の総括を行うとともに、病院長の指示を受け、院内の総ての感染対策の責任者としてその任を担うこととし、以下の業務を行う。
① ICTの業務に関する企画立案及び評価
② 感染対策に係る体制を確保するための各部門との調整
③ 医療関連感染防止対策に係る取り組み事項についての院内掲示
④ 患者・家族等からの感染対策に係る相談対応
⑤ 院内感染対策指針の見直しと改訂
⑥ その他感染対策を円滑に推進するための業務
3) 感染対策チーム (Infection Control Team:ICT)
基本方針ならびに ICC 決定事項に基づく実行部隊である。感染対策チーム(以下ICT)は、病院内における感染防止対策を充実させるための体制の強化を図り、その実践的活動を組織横断的に行う。感染防止対策全般に関する事項の具体的な提案、実行、評価などを院内感染対策委員会に対して行う。
(1)構成
感染制御医師(以下ICD) 感染管理認定看護師(以下CNIC) 感染制御認定薬剤師 (以下PIC ) 臨床検査技師 副看護部長 看護師長 医事課 放射線技師 リハビリセラピスト
(2)主な業務
① 週1回定期的なカンファレンスの開催、および緊急時の臨時会議の開催
② 各種サーベイランスによる院内感染発生状況の把握
③ アウトブレイク、異常発生時の速やかな原因究明、改善策の立案・実施による早期制圧
④ 院内感染防止対策の実施状況の調査、および効果に対する定期的な評価
⑤ 目的に応じた部署の巡回と、感染予防の観点から行う指導や改善活動
⑥ 院内感染症治療、感染防止対策に関するコンサルテーション
⑦ 微生物分離状況、薬剤感受性成績に基づく適正な抗菌薬の選択と投与方法に関する指導
⑧ 職員を対象とする教育の実施と評価、ならびに院内感染防止対策の積極的な啓発
⑨ 最新知見に基づいた院内感染防止対策マニュアルの作成、改訂
4) 抗菌薬適正使用支援チーム Antimicrobial Stewardship Team(AST)
抗菌薬適正使用支援チーム(以下AST) は、個々の患者に対して医師が抗菌薬を使用する際、最大限の治療効果を導くと同時に、副作用や薬剤耐性菌の出現といった有害事象を最小限にとどめ、早期に感染症を治療できるよう協調的支援を行う。
(1)構成
ICD CNIC PIC 臨床検査技師
(2)主な業務
① 抗菌薬を使用開始する患者を対象とし、抗菌薬使用届の記載に基づき、初期抗菌薬の適切性、微生物検査の実施状況
を早期からモニタリングする。
② 週 1 回定例カンファレンスを開催し、診療内容を電子カルテで確認、必要時主治医に確認や助言・指導を行う。
③ 抗菌薬適正使用に関する評価や抗菌薬の使用量・使用期間を体系的にまとめ、部署・部門、診療科、施設単位で情報
の伝達を行う。
④ 抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年2回実施する。なお、抗菌薬適正使用研修については、
感染対策向上加算に係る院内感染対策に関する研修と併せて実施しても差し支えない。
⑤ 抗菌薬適正使用マニュアルの作成および定期的な改訂を行う。
5) 看護部感染対策委員会(看護部感染対策委員会要綱に準ずる)
6) 院内感染対策組織図
5.医療関連感染防止のために必要な職員研修に関する基本方針
② 研修会の企画運営はICTが行い、全職員を対象とした研修を年 2 回以上開催する。また、必要に応じて、
臨時の研修を行う。これらは ICC の承認をもって職種横断的に開催する。
③ これらの諸研修の開催結果、あるいは、施設外研修の参加実績(開催または受講日時、出席者、研修項目)について
記録保存する。
6.感染症の発生状況の把握と報告に関する基本方針
① ICTは微生物サーベイランスにより微生物検出状況や感染症発生状況を監視し、必要に応じて現場介入や改善策の指導
を行う。微生物検査に関わる情報を記した感染情報レポートを週1回作成するとともに、感染症発生報告などと合わせ
てICT会議内で情報共有する。また、微生物サーベイランス結果と指導評価はICCに報告する。
② 医療関連感染サーベイランスとして、カテーテル関連血流感染、手術部位感染、人工呼吸器関連肺炎、尿路感染、
その他のデバイス関連サーベイランスを可能な範囲で実施し、感染防止対策の 改善に活用する。
7.院内感染発生時の対応に関する基本方針
① 施設内の各領域別の微生物の分離率ならびに感染症の発生動向から、医療関連感染のアウトブレイクあるいは異常発生
をいち早く察知し、制圧の初動体制を含めて迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。
② 臨床検査室の業務として、検出菌の薬剤耐性パターンなどの解析を行い、疫学情報を日常的にICT で共有、
および臨床側へフィードバックする。
③ アウトブレイクあるいは異常発生時には、当該部署長はすみやかにICTに報告する。ICTは、直ちに現場に出向き状況
を確認し、対策の指示等を行う。
④ 必要に応じて所轄の保健所へ相談し、協力と支援を要請する。
⑤ 届出が義務付けられている感染症が特定された場合には、速やかに所轄の保健所に報告する。
1) 院内感染対策組織図
8.院内感染防止対策推進のために必要なその他の事項
① 職員は、院内感染防止対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底、マスク装着の励行など、常に感染防止対策の遵守に努め る。
② 職員は、院内感染防止対策マニュアルに沿って、個人防護具の使用、リキャップの禁止、安全装置付き器材の使用など、 職業感染防止に努める。
③ 職員は、自ら感染源とならないよう、定期健康診断を年1回以上受診し、健康管理に留意するとともに、病院が実施する B型肝炎、インフルエンザおよび小児ウイルス性疾患ワクチンの予防接種に積極的に参加する。
9.地域連携に関する基本方針
① 所轄の保健所、医師会と連携し、感染対策向上加算 2 、加算 3、外来感染対策向上加算の医療機関と合同で、年 4 回
以上カンファレンスを実施し、うち 1 回は新興感染症等の発生を想定した訓練を実施する。
② 地域連携している加算 1 の医療機関と、年間 1 回以上相互に赴いて感染対策向上加算 1 に係る評価・報告を行う。
③ ICT専任医師または専従看護師は、年 4 回以上、連携する加算 2、加算 3、外来感染対策向上加 算の医療機関へ赴き
院内感染防止対策等に関する助言を行う。
④ 専従看護師は、連携する介護保険施設等から求めがあった場合、現地に赴き感染対策に係る助言を行う。
(原則として月10時間以下)
⑤ ICT および AST は、登米市内および近郊の医療機関等より、院内感染防止対策、抗菌薬適正使用に関する相談等
を受ける。
10.本指針の閲覧と策定に関する基本方針
② 患者およびご家族に疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で 協力を求める。
③ 本指針は院内感染対策委員会の議を経て適宜変更するものであり、変更に際しては最新の科学的根拠に基づき策定するよ う努める。
付 記
この指針は,平成19年 7月7日から実施する
平成24年 7月26日 改訂
平成29年 6月29日 改訂
令和元年 6月27日 改訂
令和 4年 5月 1日 改訂
令和 5年10月 6日 改訂
令和 6年 7月25日 改訂
令和 7年 4月24日 改訂
院内感染対策指針(PDFファイル 278KB)
診療情報提供に関するお知らせ
職員一同、患者様に十分納得して頂ける説明を行いますよう心がけておりますが、「説明が難しすぎる」、「説明がわかりにくい」等がございましたら、その都度お気軽に担当医師または担当職員にお尋ねください。
また、診療情報の提供(診療録(カルテ)の開示等含む)につきまして、ご不明な点またはご意見がございましたら医事係にご相談下さい。
◆お問い合わせ先: 登米市民病院 医事課
TEL0220-22-5511(内線2124)
施設基準等掲示について
医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号に掲げる手術(令和6年実績)
医療DX推進体制整備加算に係る掲示
医療情報取得加算の算定医療機関
後発品医薬品の使用促進について
バイオ後続品使用体制加算について
コンタクトレンズの処方について
一般名処方について
外来腫瘍化学療法診療料1について
連携充実加算(外来腫瘍化学療法診療料)について
◆お問い合わせ先: 登米市民病院 医事課
TEL0220-22-5511(内線2124)